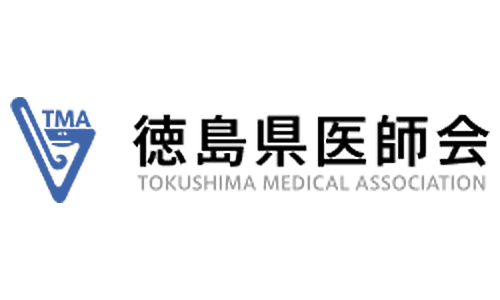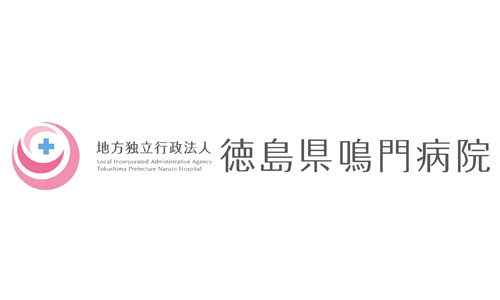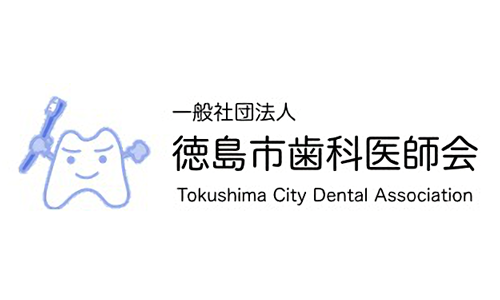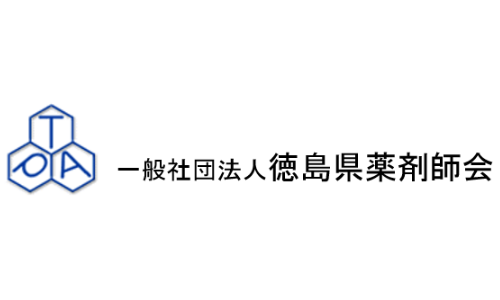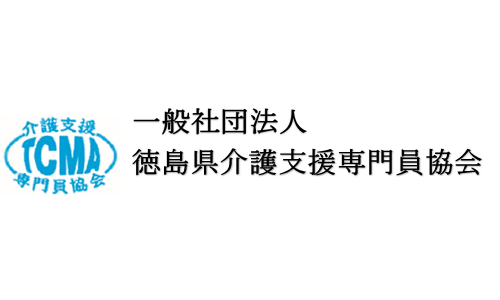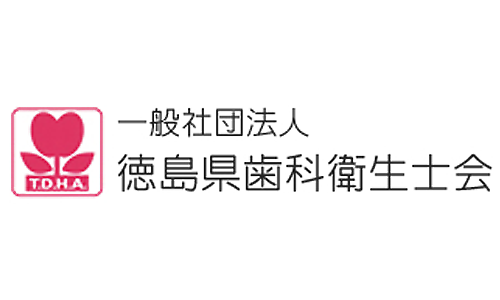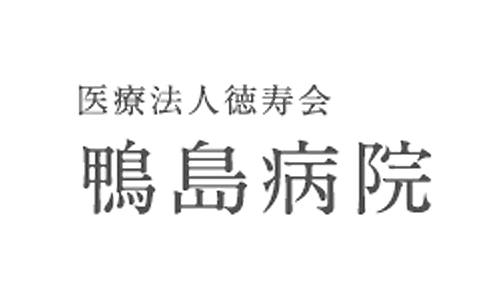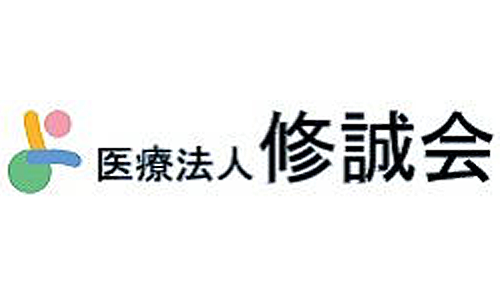離島の問題は,徳島の問題
2016年11月28日

投稿者:白山靖彦
島を訪れて間もなく,持病の耳鳴りが消え,肩こりが治った,と二人の教員が同時に呟いた.東洋のガラパゴスと言われる島の神秘パワーの効用だろうか.今回,当学が開発した口腔保健業務支援システム(ACSSOC)を高齢者施設「南風見苑」に定着させるため,南に1,500キロ離れた沖縄県八重山諸島にある最大の島「西表島」を訪問し,そこで福祉崩壊の危機に遭遇した.
西表島の人口は2,347人、世帯数1,187であり,島の90%は亜熱帯ジャングルである. 年間の平均気温が23℃で,有名な「イリオモテヤマネコ」が生息し,周りはマングローブの森とサンゴ礁が煌くエメラルドグリーンの海に囲まれている.なんと内地からの移住者が約半数を占め,小中学校と診療所,歯科診療所など一定の公共施設は,整備されている.コンビニはなく,信号機も子供たちが沖縄本島や内地に行って戸惑わない配慮から設置されたと教えられた.石垣島から高速船で40分程度であるが,夏は台風,冬は時化で海が荒れることが多く,食料の備蓄が欠かせないという.主な産業は,観光と農業である.高級なリゾートホテルや格安な民宿が点在し,年間約40万人が訪れる.島内には公共バスも走っているが,観光客の大半はレンタカーを利用し,各所を巡る.牛車が海を渡る由布島は,雑誌などで一度は目にしたことがあるに違いない.
島唯一の高齢者施設である「南風見苑」は,福祉サービスを一手に引き受けている.定員は30名で小規模デイも併設する.また,町からの委託で,外出支援や配食サービスも行っている.昨今,地域包括ケアシステムが様々な地域で推奨されているが,この島では,すでに当たり前のことなのかもしれない.ただし,海が荒れたり強い風が吹いたりすると,船やヘリが使えず,急性期医療を諦めなければならない.
利用者の多くは西表島出身者であるが,中には隣接する竹富島,石垣島から海を渡って来る人も少なくない.施設は高台に位置し,食堂の眼下には広大な澄んだ海が広がる.施設長以下,看護師,介護福祉士,介護支援専門員,栄養士,事務員など朝から利用者ケアに精を出す.職員も本島や内地から赴任した人と現地の人の割合が半々だという.
今回の訪問目的は,ACSSOCの継続を確認するためである.このシステムは,タブレット端末などを活用し,施設の看護師や介護福祉士だけでなく,外部の歯科医師や歯科衛生士と連携して利用者の口腔情報を管理するものである.導入からすでに2年が経過しており,何人かの教員が複数回訪問している.また,インターネットを介したテレビ電話にて,システムの情報交換や口腔の相談を幾度となく行ってきた.たとえ1,500キロ離れていても,双方の状況が「手に取るように」に分かる.しかし,その時間・場所でしか体感できない共有感であったり,人の関係性に脈々と流れる血のようなものであったり,を得られないのも然りである.だからこそ,そこに行き,言葉を交わし,ともに行動することが重要なのである.一般からすると異質な分野である研究であっても,その成功には人との関係性が基盤となる.
安倍政権は,「1億総活躍,介護離職ゼロ」を目指している.一方,世間では「特養増やしても、働く人がいない」,「給料を上げればそれでいいの?」などの意見が飛び交う.よく,「福祉は人である」という.まず,そこで働く人がいなければ,サービスを利用する人のQOLや幸せは保証されない.そして,『ここで働くことの喜び』を得ない限り,長くは続かないであろう.
打ち合わせの最後に,施設長が「うちの施設は,近い将来ケアマネがいなくなるかもしれない.そうなれば介護報酬全体の3割が減額され,もうやっていけない...」と.その時,離島だけの問題とは思えなかった.平成17(2005)年から平成22(2010)年の都道府県別の総人口の推移をみると,38 道府県で総人口が減少しており,この先ほとんどの地域が過疎化していくことになる.併せて福祉の担い手も減っていけば,この問題は全国に波及するに違いない.そうなる前に,人を育て,『ここで働くことの喜び』を持ってもらうしかない.
西表島には,「サガリバナ」という植物が自生していて,一年に一晩だけ美しい花を咲かせる.一夜で受粉しなければいけないので,香水のような甘い香りを出し,虫たちを呼び寄せるという.朝が来ると,ジャングルの支流一面が落ちた花で覆われる,さぞ,美しいらしい.花言葉は「幸運が訪れる」だそうだ.このサガリバナの花言葉どおり,介護する人,される人も,『ここで働くことの喜び』になればと願う.
これは,月刊福祉11号に寄稿した文章ですが,西表島の問題は,すぐに徳島の問題になるのは容易に予想がつきます.人材を育て,根づかせてこそ,包括ケアが実現するのでしょうね
西表島の人口は2,347人、世帯数1,187であり,島の90%は亜熱帯ジャングルである. 年間の平均気温が23℃で,有名な「イリオモテヤマネコ」が生息し,周りはマングローブの森とサンゴ礁が煌くエメラルドグリーンの海に囲まれている.なんと内地からの移住者が約半数を占め,小中学校と診療所,歯科診療所など一定の公共施設は,整備されている.コンビニはなく,信号機も子供たちが沖縄本島や内地に行って戸惑わない配慮から設置されたと教えられた.石垣島から高速船で40分程度であるが,夏は台風,冬は時化で海が荒れることが多く,食料の備蓄が欠かせないという.主な産業は,観光と農業である.高級なリゾートホテルや格安な民宿が点在し,年間約40万人が訪れる.島内には公共バスも走っているが,観光客の大半はレンタカーを利用し,各所を巡る.牛車が海を渡る由布島は,雑誌などで一度は目にしたことがあるに違いない.
島唯一の高齢者施設である「南風見苑」は,福祉サービスを一手に引き受けている.定員は30名で小規模デイも併設する.また,町からの委託で,外出支援や配食サービスも行っている.昨今,地域包括ケアシステムが様々な地域で推奨されているが,この島では,すでに当たり前のことなのかもしれない.ただし,海が荒れたり強い風が吹いたりすると,船やヘリが使えず,急性期医療を諦めなければならない.
利用者の多くは西表島出身者であるが,中には隣接する竹富島,石垣島から海を渡って来る人も少なくない.施設は高台に位置し,食堂の眼下には広大な澄んだ海が広がる.施設長以下,看護師,介護福祉士,介護支援専門員,栄養士,事務員など朝から利用者ケアに精を出す.職員も本島や内地から赴任した人と現地の人の割合が半々だという.
今回の訪問目的は,ACSSOCの継続を確認するためである.このシステムは,タブレット端末などを活用し,施設の看護師や介護福祉士だけでなく,外部の歯科医師や歯科衛生士と連携して利用者の口腔情報を管理するものである.導入からすでに2年が経過しており,何人かの教員が複数回訪問している.また,インターネットを介したテレビ電話にて,システムの情報交換や口腔の相談を幾度となく行ってきた.たとえ1,500キロ離れていても,双方の状況が「手に取るように」に分かる.しかし,その時間・場所でしか体感できない共有感であったり,人の関係性に脈々と流れる血のようなものであったり,を得られないのも然りである.だからこそ,そこに行き,言葉を交わし,ともに行動することが重要なのである.一般からすると異質な分野である研究であっても,その成功には人との関係性が基盤となる.
安倍政権は,「1億総活躍,介護離職ゼロ」を目指している.一方,世間では「特養増やしても、働く人がいない」,「給料を上げればそれでいいの?」などの意見が飛び交う.よく,「福祉は人である」という.まず,そこで働く人がいなければ,サービスを利用する人のQOLや幸せは保証されない.そして,『ここで働くことの喜び』を得ない限り,長くは続かないであろう.
打ち合わせの最後に,施設長が「うちの施設は,近い将来ケアマネがいなくなるかもしれない.そうなれば介護報酬全体の3割が減額され,もうやっていけない...」と.その時,離島だけの問題とは思えなかった.平成17(2005)年から平成22(2010)年の都道府県別の総人口の推移をみると,38 道府県で総人口が減少しており,この先ほとんどの地域が過疎化していくことになる.併せて福祉の担い手も減っていけば,この問題は全国に波及するに違いない.そうなる前に,人を育て,『ここで働くことの喜び』を持ってもらうしかない.
西表島には,「サガリバナ」という植物が自生していて,一年に一晩だけ美しい花を咲かせる.一夜で受粉しなければいけないので,香水のような甘い香りを出し,虫たちを呼び寄せるという.朝が来ると,ジャングルの支流一面が落ちた花で覆われる,さぞ,美しいらしい.花言葉は「幸運が訪れる」だそうだ.このサガリバナの花言葉どおり,介護する人,される人も,『ここで働くことの喜び』になればと願う.
これは,月刊福祉11号に寄稿した文章ですが,西表島の問題は,すぐに徳島の問題になるのは容易に予想がつきます.人材を育て,根づかせてこそ,包括ケアが実現するのでしょうね